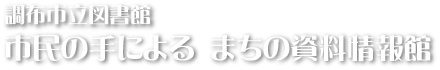<作家紹介>
野田宇太郎『文学散歩』第七巻に調布に関して次のような小見出しで紹介されています。
「大沢みち」「深大寺のうた」「祇園寺」「キアラ・岡本三右衛門」「馬琴の尼妙圓と華山の写真絵」「布多天神社と玉川調布の碑」「調布と小泉八雲の雪女」
なお「文学散歩」という語は、今日では耳馴れた言葉になっていますが、この「文学散歩」という語は野田宇太郎の造語だといわれております。
1975(昭和50)年、芸術選奨文部大臣賞受賞
<作品紹介1>
「大沢みち」というのは、野田宇太郎の造語です。戦国時代の武将箕輪将監一族にはじまる古い村里の歴史を思って、府中道の大沢から深大寺への道を大沢道と呼ぶことにしたのだと書いています。
この道が拝島道とわかれるところ、三角になった地点を昔は辻と呼んでいたそうです。ここに明治維新に京都を震撼させた新選組の隊長近藤勇の生家宮川家があります。(NHKの大河ドラマでより知名度を高め、調布の文学散歩の見所のひとつとなっています)
近藤勇が板橋で処刑されたのち、その遺体を勇の娘婿宮川勇五郎は遺体の下げわたしを請願し、許されて菰巻きの首なし遺体を、用意してきた棺に納めて荷車に乗せ、雨中を徹夜で大沢の龍源寺に運んだといわれています。戒名は「心勝院大勇儀堅居士」といいます。
<作品紹介2>
『文学散歩』の「深大寺のうた」に次のような記述があり、それを略述しましょう。
……植物公園前までくると東南に接して鬱蒼とした深大寺の森が見えた。……その先はもう御塔坂の下り勾配である。御塔坂は深大寺が関東屈指の寺として栄えた頃、高塔の聳えた坂であったことを示す歴史的名称である。……御塔坂の下り道にかかろうとする調布街道の左側路偙に一軒の茶屋があり、その店の手前から左へ曲がる道角に「深大寺」と書いた標識が立っていた。……
野田宇太郎が戦前に深大寺を訪ねたときの思い出話がつづられています。そして深大寺門前に一軒残っていた島田屋という蕎麦屋に入り、そこの主人に話を聞くのです。
「大正時代から昭和のはじめ頃までうちは博奕の客ばかり多くて、昼夜ぶっつづけで丁半とやるものだから、蕎麦もまたよく出ましたが、今はもう駄目です」と答えた。三多摩でも吉祥寺、小金井、調布あたりの農村の名物といえば、剣道と博奕といわれていました。
剣道は近藤勇の天然理心流の流れらしく、現在でもこの地方には剣道有段者が少なくないそうです。博奕は娯楽に乏しく読書などせぬ農民の手遊びで、法によって禁じられているのは昔も今も変わらないのですが、明治時代まで小金井には清水の次郎長などとも肩を並べた小金井子次郎という博奕打ちの大親分がいたのですから、その影響が戦前まで続いていたのでしょう。蕎麦屋なら寺銭も不要だし、それに深大寺では警察も遠いから、島田屋は格好の賭博場でもあったのに違いありません。
戦前の深大寺門前の風景を思い出話として書いています。そして桃山時代の建造といわれる山門をはいり、深大寺の縁起(創立の由来)にかんしては「江戸名所圖絵」にかかれている縁起を引用していますが、長文なので省略しましょう。この縁起を読んだ野田宇太郎が、次のような感想を書いているのが面白いとおもいました。「満功上人が天平五年(733年)に深大寺を開基したとき、仏典によって深沙大王のことをしり、深大寺と名づけたとみることも出来るが、満功上人の両親である福満と柏の里の長者の娘との恋愛を寺の起源としたこの縁起の著者は、なかなかのロマンチストであったと思われる」という文学者野田宇太郎らしい感想があります。
そして北原白秋がこの寺に詣でたときに詠んだ歌六首を紹介しています。
御厨子には倚像の仏坐しまして秋さなかなり響くせせらぎ
はてしらぬ仏の笑まひ面あかる灯映にしてみ掌の欠けけたる
深大寺水多ならし我が聴くに早や涼しかる滝の音ひびく
むくろじの実のまたあおき庫裡の前もの申すこえの我はありつつ
深大寺の池水澄みたらし下照りて紫紺の鯉の影行く見れば
ここの山我が聴く方ゆ日照雨して庫紺戸に濡るる秋海棠の花
<作品紹介3>
御塔坂を下り中央高速道路のガードをくぐると、左側にカトリック・サレジオ会のサレジオ修道院の正門が開いています。野田宇太郎がここを訪ねたのは、この修道院内に移されていると聞いた岡本三右衛門の墓を見るためでした。
「岡本三右衛門といっても日本人ではない。1643年禁教国の日本に潜入するために筑前大島に上陸したシシリー島バレルモ生まれの歴としたイタリア人パードレ(神父)で、その名はジュセッペ・アキラである。……はじめて切支丹屋敷ともいう小石川茗荷谷の潜入外国人専用の牢屋敷に収容された、いわばその第一号である。……しかしキアラは切支丹屋敷での拷問と役人の甘言に迷ったか、幕吏のいうままに潜入外国人の取調べなどに通訳でもするようになったのか、岡本三右衛門という日本名をもらい、切支丹屋敷内に住んで役人の仕事をしたらしいのである」
この岡本三右衛門という名の日本人が当時実在していて、外国人奉行所にいたのだが、何か重大な罪を犯して処刑されていた。キアラはその役職と俸祿と名前と岡本の妻まで譲り受け、切支丹屋敷の役人として八十四歳の生涯を終えたと言います。小石川の無量院に埋葬され、異形ながら立派な石碑が建てられていたといいます。
その後、この墓は幾度か場所を移して、いまは調布のサレジオ修道院の明るい美しい庭に、永遠にねむっているのです。
<作品紹介4>
NHKの大河ドラマ『里見八犬伝』の作者滝澤馬琴は、江戸時代文化文政期の文人ですが、この馬琴に『玄同放言』という随筆集があります。
このなかに「尼妙圓、妙圓石地蔵図付」という一項があり、尼妙圓の人となりや、渡辺華山が妙圓の建てた石地蔵を写し描いた図を載せています。
「武蔵ノ国多磨ノ郡、金子村に近きところ新造の石地蔵一躯立り、こは金子村なる、妙圓てふ尼が建立せしという」ではじまる馬琴の『玄同放言』のこの条は長いものなので、略述すると次のような話です。
金子村の百姓新助は、妻の熊と二人の子をのこして急病で亡くなりました。すると熊は親族のすすめで新助の弟と再婚しました。ところが今度は熊が病気になり、その病気の果てに両眼を失明してしまいました。熊は夫と相談して離別してもらい、深大寺住職によって剃髪、得度をうけ寿量妙圓の法名をもらい尼となりました。
金子村の村人たちは盲目の熊を憐れんで金を出しあい、念仏のための鉦をかってあげました。妙圓となった熊は、それからは毎日甲州街道の街道筋にでて鉦をたたき念仏を唱えはじめました。
その姿に心うたれた旅人達が、妙圓の前に銭を供えるようになり、その銭が数貫になったとき、妙圓は、自分がいつもでている街道脇に石造の地蔵菩薩を建立したいと思い、村人に相談するとみなも賛同しましたので、石地蔵はほどなく完成しました。1805年(文化二年)十月のことです。
街道を行き来する人々によって、妙圓尼と石地蔵の話は広く知られるようになり、妙圓尼の祈祷や加持をうけると、病気も治るといわれるようになりました。
そして十年ほど過ぎたある日、妙圓尼は突然「もう加持祈祷はしない。かえって人に迷惑になることになるかも知れないからだ」といいだしました。そして「来年の十月二十八日に念仏を唱えながら死ぬだろう」といいました。
翌年のその日、妙圓尼は元気でしたが、その翌日眠るように亡くなりました。ときに五十五歳、きよらかな死であったと伝えられています。
渡辺華山は馬琴の話をきいて、『玄同放言』のために金子村にでかけ妙圓の地蔵菩薩像を正確に写しました。野田宇太郎は、この石の地蔵菩薩像を尋ね歩き、探しえたとき、この地蔵さまは首なし地蔵という無慙なお姿だったと書いています。ただ華山の写し絵でもとの姿を想像するだけだったようです。
1987年(昭和62年)旧金子村の有志により、露仏だった地蔵菩薩の首を復元し、小堂を設けて納めました。
場所は甲州街道沿いで、菊野台派出所から二十米ほど西によったところです。
<作品紹介5>
『調布という町名は、1889年布田五宿などを合併して生まれた名称です。どうして調布なのかというと、布多天神社に由来します。布多天神社は布田宿に在り、延喜式多磨郡の官社です。
この社名に布の字を用いているのは、万葉の古歌「たまかはにさらすたつくりさらさらになにそこのこのここたかなしき」の、たつくり(調布)から名付けられたといわれています。
また「桓武天皇延暦十八年、木綿の実始めて渡りしなれど、人未だ布に製することを知らず、その時多磨川辺に広福長者といえるものあり。布を製する方術を得、本朝木綿の初めなりとかや、此により調布の里といえり」という説もありますが、年代的に真説というのは難しいそうです。
いずれにしても調布という古雅な言葉をこの町の町名とした明治の人は、立派だったなぁと感心させられます。
てづくり、また、たづくりに調布の字をあてるのは昔からの習いのようです。
<作品紹介6>
小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)の「雪女」は『怪談』の中の一編です。八雲はこの本の序文のなかで「『雪女』は、西多摩郡調布の或農夫が、その土地の伝説として、私に聞かせてくれたのである」と書いています。西多摩郡は北多摩郡の誤りと思われます。ともかく、もしこの序文がなかったら雪女が調布界隈の村里に語り伝えられた話だとならなかったでしょう。
多摩川は昔か氾濫を繰り返す荒れる川だったのです。橋は架けてもすぐながされてしまうので、渡し舟で川を行き来していました。その渡し場の雪の夜からこの話ははじまっています。
巳之吉は、冬のその日、茂作と対岸の山へ薪をとりにいきましたが、雪が降ってきたので、村に帰ることにしました。
ところが、川岸まできてみると渡し舟は対岸に繋がれていて、渡し守が見えません。雪が激しくなったので、渡し守は家に帰ってしまったらしいのです。しかたがないので、二人は船頭さんの掛小屋にとまることにしました。雪はいよいよ激しさを増してきます。二人は身を寄せあいながら、昼の疲れで寝てしまいました。
夜中に、巳之吉は何かの気配を感じ目を覚ますと、隣りに寝ている茂作の横に白い女がいて、なにかしています。
女は目をさました巳之吉に気づき、巳之吉のそばに来ました。女は若く色白で、白い着物を着ていました。奇麗な女です。巳之吉をみて微笑みました。「私はあなたは殺さない。美男子だから、……だけど、いまあなたが見たことは誰にもいってはいけない。もし誰か、それがお母さんであっても洩らしたら、あなたの命はないものと思いなさい」というと、見えなくなってしまいました。
翌朝、二人の若者が家に帰らなかったのを心配して、村人が渡し舟にのって捜しにきました。茂作は死んでいましたが、巳之吉は息をしていたので、家に連れ帰り、寝かせて看護すると、やがて元気をとりもどしました。
しかし、巳之吉はあの夜のことは女の言葉をおもいだして、誰にも話しませんでした。一年が過ぎたある冬の日、巳之吉はいつものように川を渡って山に入り、採った薪を背負って家へ帰る道を急いでいると、背の高いかわいい少女と道連れになりました。
女は名を「お雪」と名乗りました。話をしているうちにお互いに未だ結婚を約束した相手のないのを確かめ、巳之吉の家に帰り着くころには、すっかり打ち解けていました。巳之吉の母も、すぐにお雪が気に入りました。
そして程なく二人は結婚しました。その後も二人の仲のよさは村人の話題となっていました。
年月がすぎ、二人のあいだには十人の子供ができました。巳之吉の母も亡くなり、長い年月がすぎたのですが、不思議なのはお雪がいつまでも若々しく、永い年月を過ぎているのに、お雪は歳をとったようにみえないのです。
ある晩、子供たちが寝たあとで、お雪は灯りのそばで針仕事をしていました。それを見て巳之吉が、「お前がそうして顔にあかりを受けて、針仕事をしているのをみると、わしが十八のときあった不思議なことが思い出される。わしはその時、今のお前のように奇麗なそして色白な人を見た。全く、その女はお前とそっくりだったよ
」
「どこでおあいになったの」
そこで巳之吉はあの夜の話をしました。そして、「その女はたいへん白かった。私は今でもあの夜見たり聞いたりしたのは夢であったのか、現つであったのか、わからないでいる」といいました。
それを聞くとお雪は立ち上がって巳之吉の坐っているところへきて、彼の上に屈み込むようにして、彼の顔に向かって叫びました。
「それは私でした。それは雪でした。そのことを一言でも洩らしたらあなたを殺すと、その時私はいいましたね。子供達がいなかったらあなたを殺すのですが、子供達のためにあなたが必要でしょうから、やめます。子供を大事になさるがいい………」お雪の声が次第に小さくなり、姿がうすくなっていって、小屋の煙出し穴から消えていきました。
「雪女」は大体こういう話です。調布の一農民の話を。小泉八雲が見事な文学作品にまとめ上げたものでした。
明治時代の東京で小泉八雲が聞いたはなしなのですが、あるいは今も調布のどこかの家で、こんな話が伝え話されているかもしれません。
(久米)